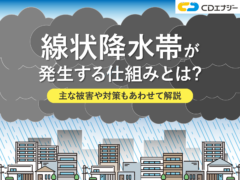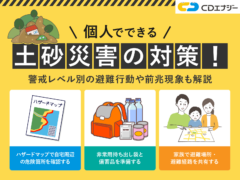東日本大震災では観測史上最大級の津波が発生し、沿岸地域を中心に大きな被害をもたらしました。
「東日本大震災の津波の高さは?」
「津波がどのくらいの被害をもたらしたのか知りたい」
このように、具体的な被害状況を知り、今後の備えに役立てたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、東日本大震災で記録された津波の高さや浸水範囲、津波が到達するまでの時間を詳しく解説します。また、津波から身を守るためにできることも紹介するため、津波に備えて、ぜひ最後までお読みください。

そもそも津波とは

津波は、地震によって海底が上下に動きし、海面が変動することで発生します。沿岸では、オリンピック短距離選手並みのスピード(時速約36㎞)で押し寄せるため、走って逃げることは困難です。ここでは、津波の高さとその特徴について解説します。津波が発生する原因をより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
【あわせて読みたい】津波が起こる原因は?イラストで仕組みをわかりやすく解説
津波の高さ
津波の高さとは、津波によって上昇した海面の高さと津波がない場合の平常潮位(へいじょうちょうい)との差のことです。また、津波が残した痕跡から推定される津波の高さは「痕跡高」、浸水の最先端が達した地盤の最大の高さは「遡上高」と呼ばれています。
気象庁が発表する「予想される津波の高さ」は、海岸線での値です。場所によっては予想よりも高くなる可能性もあるため、津波の危険性がある場合は速やかに避難しましょう。
津波の特徴
津波は強大な破壊力を持ち、広範囲に被害を及ぼす自然災害です。その特徴を以下にまとめました。
- 波浪(はろう)よりも威力が強い
- 何度も繰り返し押し寄せる
- 地形によって局所的に津波が高くなる場所がある
津波は強大な威力があり、繰り返し押し寄せるのが特徴です。複数の波が重なり、後から来る波のほうが高くなることもあるため、警報が解除されるまでは近づかないようにしましょう。また、岬の先端やV字型の湾では波の力が集中し、局所的に津波が高くなる可能性があり、特に注意が必要です。
東日本大震災の津波について

東日本大震災では巨大津波が発生し、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。ここでは、津波の高さや浸水範囲、到達時刻について詳しく解説します。
東日本大震災で記録した津波の高さ
東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県を中心とした太平洋沿岸部に、巨大な津波が襲いました。特に被害が大きかった地域の津波の高さは、以下の通りです。
国内の観測点で記録された津波の最高潮は、福島県相馬で9.3m以上でした。また、岩手県宮古では8.5m以上、岩手県大船渡では8.0m以上の津波が観測されました。
津波の影響で観測施設が破損した地域もあり、調査によると宮城県石巻市鮎川では16.7mの津波が到達したと推定されています。巨大津波によって、建物の倒壊や人的被害が発生しました。
津波の浸水範囲
東日本大震災では、津波によって宮城県や福島県を中心に広範囲が浸水したことも特徴です。浸水面積は宮城県や福島県を中心に6県62市町村で合計561㎢に及び、山手線の内側の約8.5倍の広さに相当します。
仙台平野では津波が海岸から5kmほど内陸まで到達し、大規模な浸水が発生しました。さらに、浸水した地域の4割以上で水深が2mを超えており、人や建物にも大きな影響を与えました。津波に巻き込まれると命の危険が伴うため、迅速な避難行動を心がけることが大切です。
津波の到達時刻
地震発生から第1波の津波が到達するまでの時間や、最大の高さの波が到達するまでの時間をまとめた表は以下の通りです。
被害が大きかった岩手県大船渡や宮城県石巻市鮎川などの地域では、地震発生後すぐに津波が到達したと考えられています。大船渡では、地震発生からわずか32分で8mを超える津波が襲来しました。
震源に近い地域では数分で津波が到達する可能性があるため、事前に避難経路を確認しておくことが重要です。津波の到達時間についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてみてください。
【あわせて読みたい】津波の到達時間はどれくらい?南海トラフ・東日本大震災の事例も解説
南海トラフ地震で予想される津波
今後発生が予想されている南海トラフ地震では、太平洋側を中心に大きな津波が発生する可能性があります。政府の中央防災会議が発表した津波の被害想定は、以下の通りです。
南海トラフ地震が発生すると、静岡県や和歌山県などでは10m以上の津波が予想されています。また、大阪湾や瀬戸内海でも2m以上の津波が発生する可能性があります。地震発生時は冷静な行動が難しくなるため、日頃から災害時の行動をあらかじめ想定し、備えておくことが重要です。
津波から身を守るためにできること

次に、津波から身を守るためにできることを3つ紹介します。正しい知識を身につけて、災害時に自分や大切な人の命を守れるようにしましょう。津波の対策についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考にしてください。
【あわせて読みたい】津波対策は何をすればよい?日本での取り組みや基礎知識を解説
津波標識を確認しておく
津波から身を守るために日頃から津波標識を確認し、避難経路や避難場所を把握しておくことが重要です。避難ルートを事前に知っておくことで、いざというときに迅速に行動できます。津波標識の種類は以下の通りです。
津波の危険がある地域では、頑丈で高い建物を津波が発生したときの一時避難場所として指定している場合もあります。万が一、海沿いで地震が発生した際は、津波避難場所や津波避難ビルへすぐに逃げ込み、安全を確保しましょう。
正しい情報を入手する
災害時には正しい情報を入手し、落ち着いて行動することが大切です。災害発生時は多くの人々が不安を感じ、根拠のないうわさやデマが広がりやすくなります。
たとえば、SNSで拡散された情報を安易に信じると、誤った行動を取る可能性があります。テレビやラジオ、防災行政無線などの信頼できる情報源を活用し、正しい情報をもとに冷静な判断を心がけましょう。
より高い場所に逃げる
津波から身を守るためには遠くへ逃げるのではなく、より高い場所に避難しましょう。津波は水深の浅い場所でも時速36kmほどの速さで押し寄せるため、人が走って逃げるのは困難です。また、沿岸の地形によって津波が局所的に高くなることもあります。
実際に過去の津波被害では、高台に逃げ遅れた方が流されるケースもありました。さらに、後から来る津波のほうが高くなることもあります。警報が解除されるまでは油断せず、できる限り高い場所で安全を確保しましょう。
東日本大震災に関するよくある質問

最後に、東日本大震災に関するよくある質問に回答します。
震度や被害が大きくなった理由を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
東日本大震災の最大震度は?
東日本大震災では、宮城県栗原市で最大震度7が観測されました。宮城県、福島県、茨城県、栃木県では震度6強の揺れを記録し、それ以外の地域でも震度6弱から震度1の揺れが発生しました。
その後、2011年4月7日に宮城県沖を震源とした震度6強の地震が発生するなど、多くの余震も観測されています。東日本大震災の各地の震度については、以下の記事で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい】東日本大震災の震度はどれくらい?人的被害や津波による被害も詳しく解説
東日本大震災で被害が大きかった理由とは?
東日本大震災では、最大震度7の地震と巨大津波、頻発する余震が重なったことで大きな被害が発生しました。特に津波の被害は大きく、建物が倒壊・流出し、鉄道や道路などの交通インフラも損なわれました。
さらに、津波や余震に伴って発生した地盤沈下や液状化、火災なども被害を大きくした原因です。火災が発生しても十分な消火活動ができずに広範囲に延焼し、大きな被害をもたらしました。
災害が起きる前に身を守る準備を進めよう!
本記事では、東日本大震災における津波の高さについて解説しました。津波は広範囲にわたって浸水被害をもたらし、福島県相馬では9.3m以上の津波が町に押し寄せました。
陸・海・空を管轄する国土交通省の出先機関のトップを務めた官僚は、「備えていたことしか役に立たなかった」と語っています。災害時に冷静に行動し、命を守るためには日頃の備えが欠かせません。避難経路の確認や非常用品の準備など、今からできる対策を進めましょう。