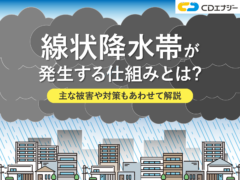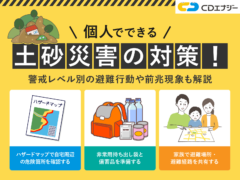「東日本大震災の最大震度は?」
「どのくらいの被害だったのか知りたい」
「地震が起きたらどうすればいいの?」
東日本大震災は東北地方を中心に、日本の広範囲に深刻な影響を与えました。震度や津波の高さに関して具体的に知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、東日本大震災の震度や津波による被害の規模、人的被害について詳しく解説します。また、津波発生時に取るべき行動も紹介するので東日本大震災の影響を理解し、将来に活かすためにぜひ最後までお読みください。

東日本大震災で観測された全国の震度

2011年3月11日の東日本大震災では、宮城県栗原市で最大震度7を観測しました。宮城県・福島県・茨城県・栃木県でも震度6強の揺れが発生しました。東日本大震災の全国の震度は以下の通りです。
宮城県牡鹿半島の東南東130km付近の深さ約24kmを震源とし、北海道から九州まで、日本の広い範囲で震度7〜震度1の揺れを観測しました。2011年4月7日には宮城県沖を震源として震度6強を記録するなど、余震が多発したことも特徴です。東日本大震災のマグニチュードは9.0で、1900年以降、世界で観測された地震のなかで4番目の規模でした。
東日本大震災における影響と被害
東日本大震災では地震だけでなく、津波や火災など複数の災害が重なり、多くの命が失われました。ここでは、東日本大震災による影響と被害について詳しく解説します。津波による被害や交通機関・インフラへの影響について知りたい方はぜひ参考にしてください。
人的被害
東日本大震災での死者・行方不明者は12都道府県でみられ、死者が1万5,859人、行方不明者が3,021人(平成24年5月30日警察庁発表)です。これは関東大震災、明治三陸地震に次ぐ規模でした。
特に被害が大きかった岩手県・宮城県・福島県の死者のうち、溺死が92.4%を占めています。津波による被害が主な原因で、多くの命が奪われました。
津波による被害
東日本大震災では、岩手県・宮城県・福島県を中心に巨大な津波が襲い、人や建物に大きな影響を与えたことも特徴です。特に大きな津波が襲ったのは以下の地域でした。
| 地域 | 津波の高さ |
|---|---|
| 福島県相馬 | 9.3m以上 |
| 岩手県宮古 | 8.5m以上 |
| 岩手県大船渡 | 8.0m以上 |
このほか、宮城県女川漁港では14.8mの津波痕跡も確認されています。
また津波による浸水が広範囲にわたり、沿岸部を中心に被害が拡大しました。国土地理院によると、青森県から千葉県にかけての6県の浸水合計面積は561km²です。この面積は山手線の内側の約9倍に相当します。
地殻変動
東日本大震災の影響で、東北から関東の広い地域で地殻変動も観測されています。宮城県牡鹿半島周辺では水平方向に5m以上の変化が観測され、震災後の変動も含めると10年間で6m以上に達しました。また同地域では1m以上沈降し、その後隆起したものの、震災後の変動を含めると10年間で約50cmの沈降が確認されています。
交通機関・インフラへの影響
東日本大震災では首都圏でも震度5強を観測し、交通機関に大規模な乱れが生じたことで多くの帰宅困難者が発生しました。
また、茨城県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県では液状化現象も発生し、砂の噴出でマンホールが浮き上がったり、電信柱が傾斜・沈下したりするなどの被害が出ています。ライフラインも一時的に停止し、断水や停電が発生するなど、生活基盤にも大きな影響をおよぼしました。
【シチュエーション別】地震発生時に取るべき行動

地震はいつどこで発生するかわかりません。ここでは、地震発生時に取るべき行動をシチュエーション別に解説します。想定するのは、以下のシチュエーションです。
状況によって最善の行動は異なるので、日頃から確認して災害時に冷静な行動を取れるようにしておきましょう。
自宅にいるとき
自宅で地震が発生した場合、まずは家具やガラスから離れ、テーブルやベッドの下に身を隠して安全を確保しましょう。トイレや浴室にいる場合は、ドアが変形して閉じ込められる可能性があるため、ドアを開けて避難経路を確保することが大切です。
都市ガスやプロパンガスは震度5程度の揺れで供給が停止するため、火の元は揺れがおさまってから確認すれば問題ありません。深夜に地震が起きた場合は布団をかぶって頭と体を守り、揺れがおさまるのを待ちましょう。
スーパー・お店の中にいるとき
まずはエレベーターホールや階段近くなど、落下物の少ない場所に移動して身を守りましょう。
スーパーやお店の中にいるときに地震が発生した場合、商品やショーケースの転倒・落下の危険があります。姿勢を低くして頭を保護し、揺れがおさまるのを待ちましょう。
その後は慌てずに係員の指示に従い、安全な場所へ避難することが大切です。非常口の位置を普段から意識しておくと、いざというときに迅速に行動できます。
海・山にいるとき
海の近くでは津波の危険があるため直ちに海から離れ、できるだけ高い場所へ避難しましょう。津波は繰り返し押し寄せる可能性があり、後から来る波の方が高くなることもあります。そのため、警報が解除されるまでは絶対に海に近づかないようにしてください。
山では落石や崖崩れのリスクがあるため、周囲の状況をよく確認しながら危険な場所から速やかに移動しましょう。避難時は足元に注意し、不安定な地形を避けることが安全確保につながります。
住宅地・オフィス街にいるとき
屋外では自販機や電柱、建物、看板の落下・倒壊の危険があるため、カバンや上着で頭を守り、揺れがおさまるのを待ちます。揺れがおさまったら倒壊の恐れがあるビルから離れるか、頑丈な建物の中に避難しましょう。
特にビルが多い場所では外壁や窓ガラス、看板などが落下して怪我をする可能性があります。身を守るために通勤時の避難場所を事前に確認し、落ち着いて行動できるよう準備しておくことが大切です。
東日本大震災に関するよくある質問

最後に東日本大震災に関するよくある質問に回答します。
東日本大震災で被害が大きくなった原因や、揺れについて詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
東日本大震災は何分揺れた?
東日本大震災の揺れは約3分続きました。断層の規模が大きく、破壊が完了するまでに時間がかかったため、過去の地震と比べても長く揺れたことが特徴です。
1978年の宮城県沖地震と比較すると継続時間は3倍以上であり、揺れの長さが被害の拡大につながりました。長時間の揺れにより建物の倒壊や地盤の液状化が進み、多くの地域に甚大な被害をもたらしたのです。
東日本大震災で大きな津波が発生した原因は?
東日本大震災で大津波が発生した原因は、水深6,000m以上の海溝で起きた海溝型地震であったためと考えられています。しかし、なぜあれほど大きな津波となったのか、すべての原因が解明されているわけではありません。
まずは地震と津波のメカニズムについて解説します。日本列島は以下の4つのプレートの境界に位置しています。

太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込む際に、摩擦で北米プレートが引き込まれてひずみが蓄積します。ひずみが限界に達して北米プレートが一気に跳ね上がると、地震が発生します。この地震で海水が押し上げられることによって津波が発生するのです。
東日本大震災もプレート間の海溝で発生した地震でした。そして、大津波の発生原因については、専門家の研究により、以下のような仮説が挙げられています。
- 断層のずれが広範囲におよんだことで日本海溝に近い海底が動き、多くの海水が持ち上げられたため
- プレートの比較的やわらかい部分が大きくゆっくりと動く「津波地震」と、大規模な「海底地すべり」が発生したため
なお、東日本大震災の津波の高さについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい】東日本大震災の津波の高さはどれくらい?浸水範囲や到達時刻も詳しく解説
東日本大震災の教訓を学び、防災意識を高めよう!
本記事では、東日本大震災の震度について解説しました。大きな地震が起きた場合、身の安全を確保することを最優先し、揺れがおさまったら避難の準備をします。
また津波の危険性がある場合は海から離れて、指定された避難所や高台へ向かいましょう。津波は何度も押し寄せる場合もあるため、警報が解除されるまでは海や川には近づかないようにしてください。
災害時に冷静に行動するためには、普段から避難場所や避難経路を確認しておくことが大切です。東日本大震災の教訓を学び、今後地震が発生した際は冷静に行動できるように準備しましょう。