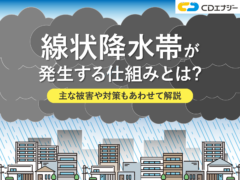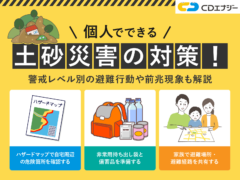「子ども向けに防災の日を説明するにはどうすればよい?」
「子ども向けの避難訓練とは?」
「子ども向けの防災グッズについて知りたい」
防災の日について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。保育園や幼稚園では、子ども向けクイズや絵本の読み聞かせで防災教育がおこなわれます。家庭では地方自治体がおこなう防災イベントやインターネット上のコンテンツが利用可能です。
この記事では、防災の日に子ども向けにできることについて解説します。ほかにも、遊びながら学ぶ方法や、子ども向けの防災グッズについて触れていきます。
この記事を読むことで、防災の日に子どもとどのように向き合えばよいのかがわかるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
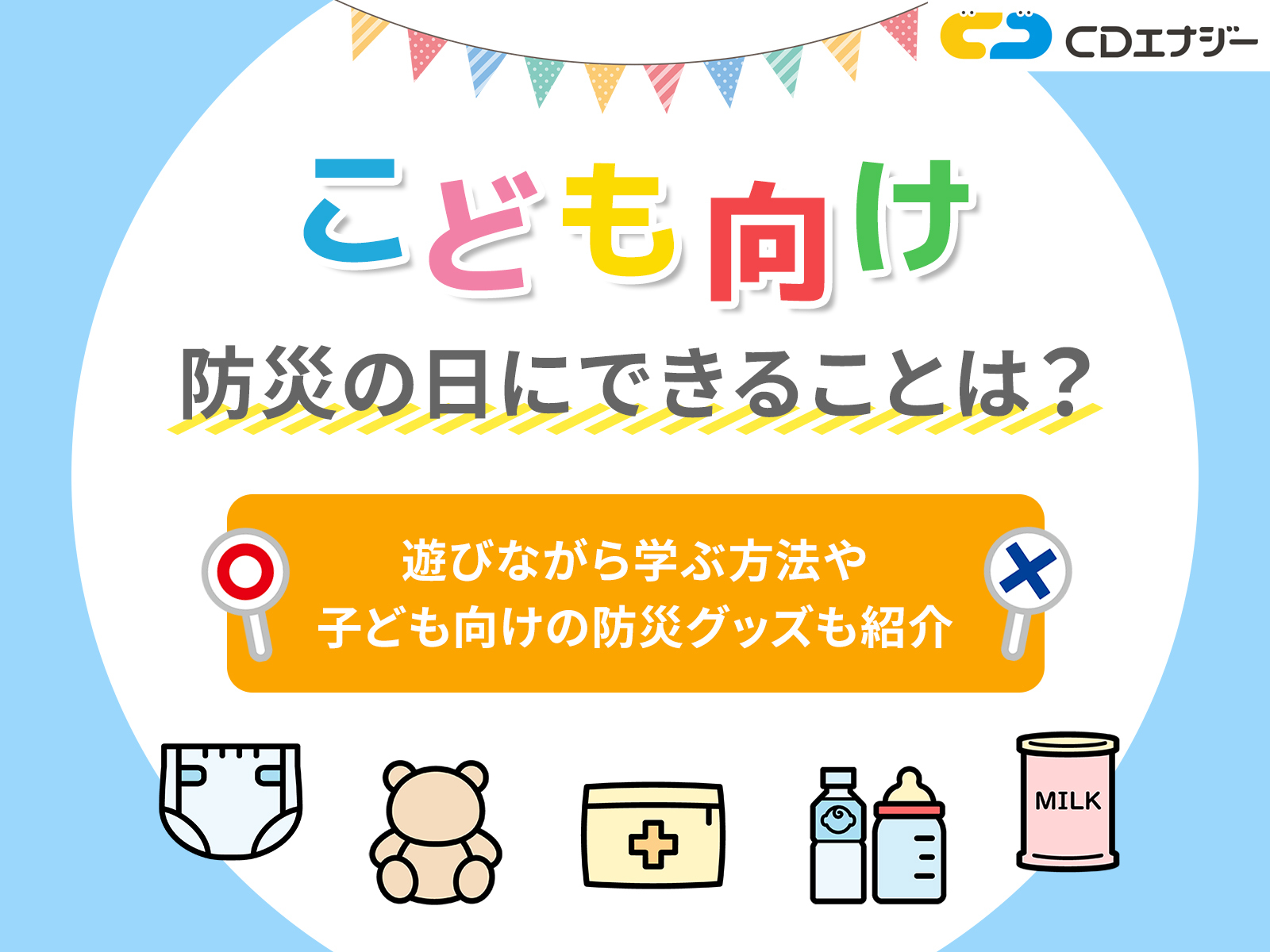
- 防災の日とは
- 防災の日の由来
- 防災の日を子ども向けに伝える方法
- 防災の日に保育園・幼稚園でおこなうこと
- 子ども向けの防災クイズを出す
- 防災の絵本や紙芝居を読み聞かせする
- 給食に非常食を提供して食育をおこなう
- 保護者参加の引き取り訓練をおこなう
- 防災の日に家庭で子どものためにできること
- 1. 子どもと一緒に防災訓練ゲームで遊ぶ
- 2. 子ども向けの防災イベントに参加する
- 3. 子ども向けの防災グッズを準備・点検する
- 4. 避難経路・家族の連絡手段を確認する
- 災害が発生した際に取るべき行動
- 1. 身の安全を確保する
- 2. 揺れがおさまったら避難する
- 3. 情報収集や状況確認をおこなう
- 防災の日に関するよくある質問
- 9月1日が防災の日になったのはなぜ?
- 防災の日は何をする?
- 防災の日はなぜできた?
- 防災の日は子どものために災害対策をおこなおう
防災の日とは

防災の日とは、自然災害に対する備えの重要性を広めるために制定された日です。1960年に制定され、毎年9月1日に災害への備えを促進するイベントや訓練で周知がおこなわれています。
【あわせて読みたい】防災の日とは?何をする?制定の背景・やるべきことも解説
防災の日の由来
9月1日が防災の日として制定されたのは、関東大震災が1923年9月1日に発生したことが由来です。この地震により、死者と行方不明者を合わせて10万5千人以上が被害に遭いました。
また、9月1日は旧暦の「二百十日」に当たり、台風シーズンが始まるタイミングでもあります。1959年9月26日には伊勢湾台風により戦後最大の被害がもたらされました。
こうした事情から、政府や地方自治体、そして国民一人ひとりが備える日として、防災意識を高める機会となっています。
防災の日を子ども向けに伝える方法
防災の日を子どもにわかりやすく伝えるためには、難しい言葉を使わずに伝えることがポイントです。たとえば「地震や台風が起きたときのために、避難訓練をしたり防災グッズを揃えたりする大切な日」であることを伝えましょう。
また、言葉ではうまくイメージできない子どももいるため、防災に関する絵本や紙芝居を活用して視覚的に学ぶのもおすすめです。
防災の日に保育園・幼稚園でおこなうこと

災害について理解を深めるため、防災の日には保育園や幼稚園で以下のような取り組みがおこなわれます。
ここからは、それぞれの取り組みについて解説します。
子ども向けの防災クイズを出す
防災に関するクイズは、遊びながら学ぶのに役立つ方法です。クイズ形式で、避難経路や災害時の行動についての理解を深められます。
出題方法はいくつかありますが、最もシンプルなのは〇×クイズです。たとえば「地震が起きたらすぐに外に出る」など防災に関する問題を出題し、子どもたちには〇か×かで答えてもらいます。
東京消防庁は子ども向けの「リモート防災学習」を公開しています。子どもの発達段階に応じて表現を工夫すると、より楽しく学べるでしょう。
防災の絵本や紙芝居を読み聞かせする
絵本や紙芝居で読み聞かせすることで、子どもたちも楽しく防災について学べます。
絵本は聴覚と視覚の両方にアプローチできるため、子どもも理解しやすいのがメリットです。園によっては先生が手作り紙芝居で防災のストーリーを披露することもあります。
絵本や紙芝居を通じて協力や助け合いの大切さを学び、実際の災害に備える意識を育めます。
給食に非常食を提供して食育をおこなう
防災の日に非常食を給食に取り入れ、食育をおこなう保育園や幼稚園もあります。非常食は普段食べ慣れていないものが多いため、味や食べ方に慣れる機会になるでしょう。
たとえばアルファ化米のご飯やレトルトカレー、わかめや切り干し大根などの乾物を使ったメニューを提供することで、災害時の食事を体験できます。非常食の種類や作り方などを楽しみながら学ぶことで、災害への備えを身につけられます。
保護者参加の引き取り訓練をおこなう
防災の日には、保護者が参加する引き取り訓練を実施することがあります。これは、災害や緊急時に保育園や学校で子どもを安全に引き渡すための訓練です。
子どもが施設にいるときに災害が発生した場合、保護者は指示に従い、決められた方法で子どもを迎えに行きます。この訓練を通じて、保護者は災害時の対応方法を確認し、子どもの安全を守る準備ができます。
保育園や幼稚園で引き取り訓練をおこなう際には、避難場所やお迎え方法を事前に連絡しておくことが重要です。
防災の日に家庭で子どものためにできること

防災の日は、家庭で子どもと一緒に災害への備えを確認するよい機会です。小さな子どもがいる家庭では、以下のような方法で楽しく学んだり、備えたりすることが大切です。
ここからは、それぞれの方法について解説します。
1. 子どもと一緒に防災訓練ゲームで遊ぶ
防災の日に子どもと一緒に防災訓練ゲームで遊ぶことで、楽しく学習できます。東京消防庁が公開している「おうちで防災を学ぼう!リモート防災学習」は、家族で視聴できるオンラインの防災学習コンテンツです。
このほか、カードゲームやスマホアプリを使った防災ゲームもあります。遊びながら避難方法や安全確保の知識を身につけられるため、自然と防災意識を高められます。
2. 子ども向けの防災イベントに参加する
子ども向けの防災イベントに参加することで、地域に根づいた防災意識を学べます。災害の影響は地形や環境によって大きく異なるため、住む地域に応じた訓練を体験することが大切です。
子ども向けの防災イベントは、体験型の防災訓練やクイズラリー、謎解きなど、遊びながら学べる工夫が施されています。親子で一緒に参加することで、家庭内での防災意識も高まります。
また、地域の特性に合わせた内容があれば、実際の災害時に役立つ知識を身につけられるのも大きなメリットです。
3. 子ども向けの防災グッズを準備・点検する
子ども向けの防災グッズは、年齢や成長段階に合わせて準備することが大切です。以下は、乳幼児がいる家庭に必要な防災グッズです。
| 乳幼児がいる家庭に必要な防災グッズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 母子健康手帳 健康保険証 オムツ お尻ふき 授乳用ケープ ミルクセット 紙コップ スプーン キッチン用ラップ ガーゼ |
抱っこ紐 非常食 離乳食 ビタミン剤 着替え 靴 防寒具 マスク おもちゃ |
|||||
小学生以降は基本的に大人と同じ防災グッズで問題ありませんが、マスクや軍手、ヘルメットなどのアイテムは子ども用サイズを用意しましょう。また、トランプや持ち運び用のボードゲームなど気分転換できるグッズもあると安心です。
防災グッズは、定期的に点検して賞味期限をチェックしましょう。子どもの成長に合わせて見直すことで、いざというときに備えられます。
4. 避難経路・家族の連絡手段を確認する
災害時に家族全員が安全に避難するためには、避難経路と連絡手段を事前に確認しておくことが重要です。自宅や学校、よく行く場所からの避難ルートを確認し、最寄りの避難場所や避難ビルを把握しておきましょう。
集合場所を3箇所ほど決めて優先順位をつけることで、家族が離ればなれになった場合でも再会しやすくなります。また、災害時には電話やメールがつながりにくくなる可能性があるため、災害用伝言板やSNSなどの連絡手段を決めて、使い方を共有しておくと安心です。
災害が発生した際に取るべき行動

災害が発生したときは、冷静に以下のような行動をとることが必要です。
ここからは、それぞれの行動について解説します。
1. 身の安全を確保する
地震が発生した際は、まず落ち着いて身の安全を確保することが最優先です。頭を守るために、ヘルメットや近くにあるクッションを使用しましょう。丈夫なテーブルの下に身を隠し、揺れがおさまるまで待つのが基本的な行動です。
また、ものが「落下しない」「転倒しない」「移動しない」場所に避難することで、怪我のリスクを減らせます。
2. 揺れがおさまったら避難する
地震の揺れがおさまった後は、状況に応じて安全に避難することが重要です。
家にいる場合は、揺れがおさまったことを確認してから避難します。コンロなど火を使用している場合は、揺れがおさまってから火を消します。施設にいる場合は、従業員の指示に従って安全に行動しましょう。
屋外にいる場合は、看板やガラスの落下に注意しつつ、安全なビルに避難します。海岸近くにいる場合は、津波の危険があるため速やかに高台へ避難してください。
3. 情報収集や状況確認をおこなう
災害時は、できるだけ信頼できる情報源を利用するように努めましょう。最新の状況や避難指示に関する情報収集は、テレビやラジオ、防災行政無線の利用がおすすめです。
SNSやインターネットを利用する場合は、政府や地方自治体の公式情報を優先しましょう。複数の情報源を確認する習慣を身につけることで、誤情報に惑わされにくくなります。
防災の日に関するよくある質問

ここでは、防災の日に関するよくある質問についてまとめました。
それぞれの質問に回答します。
9月1日が防災の日になったのはなぜ?
9月1日が防災の日になったのは、1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しているからです。この大震災では、10万人以上が命を落とし、日本における防災意識の重要性が痛感されました。
さらに、9月1日は旧暦の「二百十日」にあたり、台風シーズンの始まりでもあります。1959年9月26日の伊勢湾台風は戦後最大の被害となりました。そのため、政府は1960年に9月1日を防災の日として制定し、地震や台風などの自然災害に対する警戒心と備えを促す日としました。
防災の日は何をする?
家族と一緒にハザードマップを確認し、災害に備えた準備を整えましょう。すでに防災バッグを準備している場合も、定期的な点検で賞味期限をチェックし、子どもの成長に合わせて中身を見直す必要があります。
また、家族で防災訓練に参加するのもおすすめです。避難訓練やシェイクアウト訓練(地震時の安全確保行動)を通じて、災害時に備えるための実践的なスキルを学べます。
防災の日はなぜできた?
防災の日が制定された目的は、一人ひとりの防災対策の重要性を国民に広く理解してもらうためです。1923年9月1日に発生した関東大震災は、10万人以上が命を落とし、多くの人々が家を失うという大災害でした。また、1959年9月26日の伊勢湾台風は戦後最大の被害をもたらしました。
災害時は政府や地方自治体の防災対策はもちろん、一人ひとりの意識と行動が命を守る鍵となります。そのため、政府は9月1日を「防災の日」と定め、日頃から万全の準備を整えるための日としたのです。
防災の日は子どものために災害対策をおこなおう
防災の日は、子どもたちにも災害への備えの大切さを伝えるよい機会です。家庭や学校で防災訓練をおこなったり、子ども向けの絵本やクイズを通じて災害への理解を深めましょう。
また、避難経路や連絡手段の確認、非常食の準備なども家族全員で一緒におこなうことで、災害時の不安を減らし、安心感を与えられます。
防災の日の過ごし方を考える際は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてください。