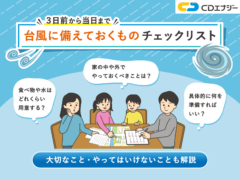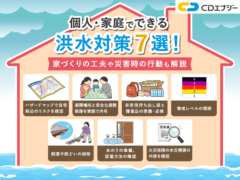「能登半島地震の震度はどれくらい?」
「どれほどの被害が出たのか詳しく知りたい」
能登半島地震の揺れの大きさや被害の状況について、より詳しく知りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
能登半島地震は、2024年に石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震です。最大震度7を記録した地域では、建物の倒壊やライフラインの寸断など深刻な影響が出ています。発生後も2024年3月末までに震度7が1回、震度6弱が2回、震度5強が8回、震度5弱が7回の余震が発生しています。
この記事では、能登半島地震の震度や被害状況をわかりやすく解説します。さらに、今後懸念される南海トラフ地震で想定される震度についても紹介します。災害への理解を深めて対策をしたい方は、ぜひ最後までお読みください。

能登半島地震の震度一覧
2024年1月1日に石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、石川県輪島市と志賀町で震度7を観測しました。七尾市や珠洲市などでは震度6強、そのほかでも北海道から九州にかけて広範囲で揺れが観測されました。能登半島地震による全国の震度は以下の通りです。
その後も2024年3月末までに震度7が1回、震度6弱が2回、震度5強が8回、震度5弱が7回の余震が発生しました。震度1以上の地震は合計1,772回にのぼっています。
能登半島地震による被害

能登半島地震では、住宅の倒壊や火災、道路の寸断など多くの深刻な被害が発生しました。特に石川県では甚大な被害が集中し、避難生活を余儀なくされた方も多数います。ここでは、能登半島地震による被害を解説します。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
人的被害
能登半島地震では、石川県を中心に多数の人的被害が報告されています。主な内訳は以下の通りです。
| 死者(うち災害関連死) | 行方不明者 | 負傷者 |
|---|---|---|
| 549名(321名) | 2名 | 1,393名 |
出典:令和6年能登半島地震による被害及び消防機関等の対応状況(第118報)|消防庁
特に被害が大きかったのは石川県の輪島市や珠洲市です。建物の倒壊・損壊に加え、輪島市では市街地で火災が発生し、地震との複合的な被害によって多くの死傷者が出ました。
液状化現象による被害
能登半島地震では、新潟県、富山県、石川県、福井県の広い地域で液状化も報告されています。液状化現象とは、地震によって地盤が揺さぶられ、地盤全体ドロドロの液体のような状態になることです。地下水とともに砂や泥が地表に噴き出したり、建物が沈んだり傾いたりするなどの現象が発生します。
富山県魚津市では震度4を観測し、港周辺の駐車場で複数箇所に液状化現象が発生しました。地震の規模が大きく、揺れが長時間続いたことや、地下水位が高く砂地が多い沿岸地域の地盤が影響したと考えられています。
停電・断水
地震により広範囲で停電・断水も発生し、輪島市や珠洲市を中心に最大約40,000戸で停電しました。ただし、送電線や変電所の大きな損傷は見られず、広域停電には至っていません。一方で、土砂崩れやがれきによってアクセス困難な場所が多く、復旧には時間を要しました。
断水はさらに深刻で、影響を受けた世帯は最大約137,000戸にのぼります。ライフラインの途絶は避難生活の長期化にもつながり、被災者の暮らしに大きな影響を与えました。
住家被害
能登半島地震では、石川県、富山県、新潟県を中心に多数の住家被害も発生しました。住家被害の内訳は以下の通りです。
| 全壊 | 半壊 | 一部破損 |
|---|---|---|
| 6,483棟 | 23,458棟 | 133,758棟 |
石川県や新潟県では一部で床上・床下浸水も確認されました。さらに、輪島市では大規模火災や液状化現象が重なったことで、住家への影響が深刻化しました。
南海トラフ地震で想定される震度
政府の中央防災会議では、南海トラフ巨大地震が発生した際の被害想定を発表しています。各地域で想定される震度は以下の通りです。
静岡県から宮崎県にかけての一部で震度7の揺れが想定されており、それ以外の広い地域で震度6強や6弱の強い揺れが予想されています。また、同時に大規模な津波が発生する可能性も高く、甚大な被害が懸念されます。こうした想定を踏まえ、地震発生時には一刻も早く行動することが、自分や家族の命を守るために重要です。
【場所別】地震発生時に取るべき行動

地震はいつどこで起こるかわかりません。地震発生時にとっさの判断が求められるからこそ、事前に適切な行動を理解しておくことが大切です。
ここでは、地震発生時に取るべき行動を場所ごとに解説します。
屋内にいる場合
まずは、身の安全を確保することが最優先です。地震が発生したら、すぐにテーブルや机の下に潜って頭を守りましょう。揺れている最中に外に飛び出すと、落下物でケガをする可能性があり危険です。
浴室やトイレにいる場合は、ドアを開けて出口を確保しましょう。火を使っている場合も、無理に消そうとせず、揺れが収まってから火の処理をおこないます。
屋外にいる場合
屋外にいる場合は、落下物から身を守る行動を優先しましょう。地震の際は、ビルの外壁やガラス、看板などが落ちてくる危険があります。その場にしゃがみこみ、手や荷物で頭を守りながら揺れが収まるのを待ちます。
近くに丈夫な建物がある場合は、その中に一時的に避難して身の安全を確保しましょう。周囲の状況を見て、冷静に判断することが大切です。
海・川の近くにいる場合
海や川の近くでは津波の危険があるため、地震が発生したらすぐに高台へ避難してください。津波はわずか数分で押し寄せることもあります。少しの揺れでも迷わず、陸側の高い場所へ逃げましょう。
また、津波は1度で終わらず、何度も繰り返し襲ってくる点が特徴です。東日本大震災では、第一波が引いたあと、家に戻ったことで被害にあうケースも多くありました。津波警報が解除されるまでは海辺へ戻らないようにしましょう。
能登半島地震に関するよくある質問

最後に、能登半島地震に関するよくある質問に回答します。
津波の被害や復興状況について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
能登半島地震による津波の被害は?
能登半島地震では、北海道から長崎県にかけて津波が観測されました。主な観測地点と津波の最大の高さは以下の通りです。
| 観測地点 | 最大の高さ |
|---|---|
| 石川県金沢 | 80㎝ |
| 山形県酒田 | 80㎝ |
| 富山県富山 | 79㎝ |
| 鳥取県境港市境 | 60㎝ |
輪島港や珠洲市長橋付近では、地震直後から、観測記録が得られていませんでしたが、後の調査で津波による浸水は確認されませんでした。
能登半島地震の復興状況は?
能登半島地震の復興は徐々に進んでいます。9月の豪雨による影響も含め、命に関わるような被災箇所への応急対策はすでに完了しました。仮設住宅の手配も完了し、多くの方が避難所からの生活再建を果たしています。
また、恒久的な使用も見据えた木造の応急仮設住宅の供給も始まっており、住環境の改善が進行中です。さらに、建物倒壊地域を除く多くの地域では、水道本管の復旧も完了しています。
能登半島地震が発生した原因は?
能登半島地震は、複数の断層が連動して動いたことが主な原因とされています。能登半島の南西側から佐渡島方向にかけて延びる複数の断層が一斉にずれ動いたことで、大きな揺れが発生しました。
万が一に備えて、災害時の行動を把握しておこう!
本記事では、能登半島地震の震度や被害について詳しく解説しました。震度7を記録した地域では、建物の倒壊や火災、津波、液状化現象などの被害が重なり、生活基盤への深刻な影響が生じました。
また、今後発生が懸念される南海トラフ地震では、さらに広範囲で強い揺れが想定されています。地震はいつどこで発生するかわからないからこそ、正しい知識を持ち、災害時の行動を理解しておくことが大切です。日頃からの個人でできる備えを進め、自分や大切な人を守りましょう。