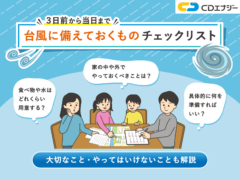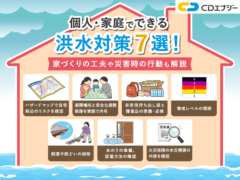「地震速報で誤報が発生するのはなぜ?」
「揺れたのに地震情報がない理由は?」
「緊急地震速報の仕組みは?」
地震速報で誤報が発生する現象について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
地震速報で誤報が発生する原因の多くは、システムの誤差・誤作動によるものです。震源の近くや予測震度が急に上がると速報が間に合わない場合もあります。ほかにも、スマホの緊急速報の受信設定がOFFになっていると速報が届かないため、注意してください。
この記事では、地震速報で誤報が発生する原因について解説します。ほかにも、揺れたのに情報がない原因について触れていきます。
この記事を読むことで地震速報について理解が深まるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
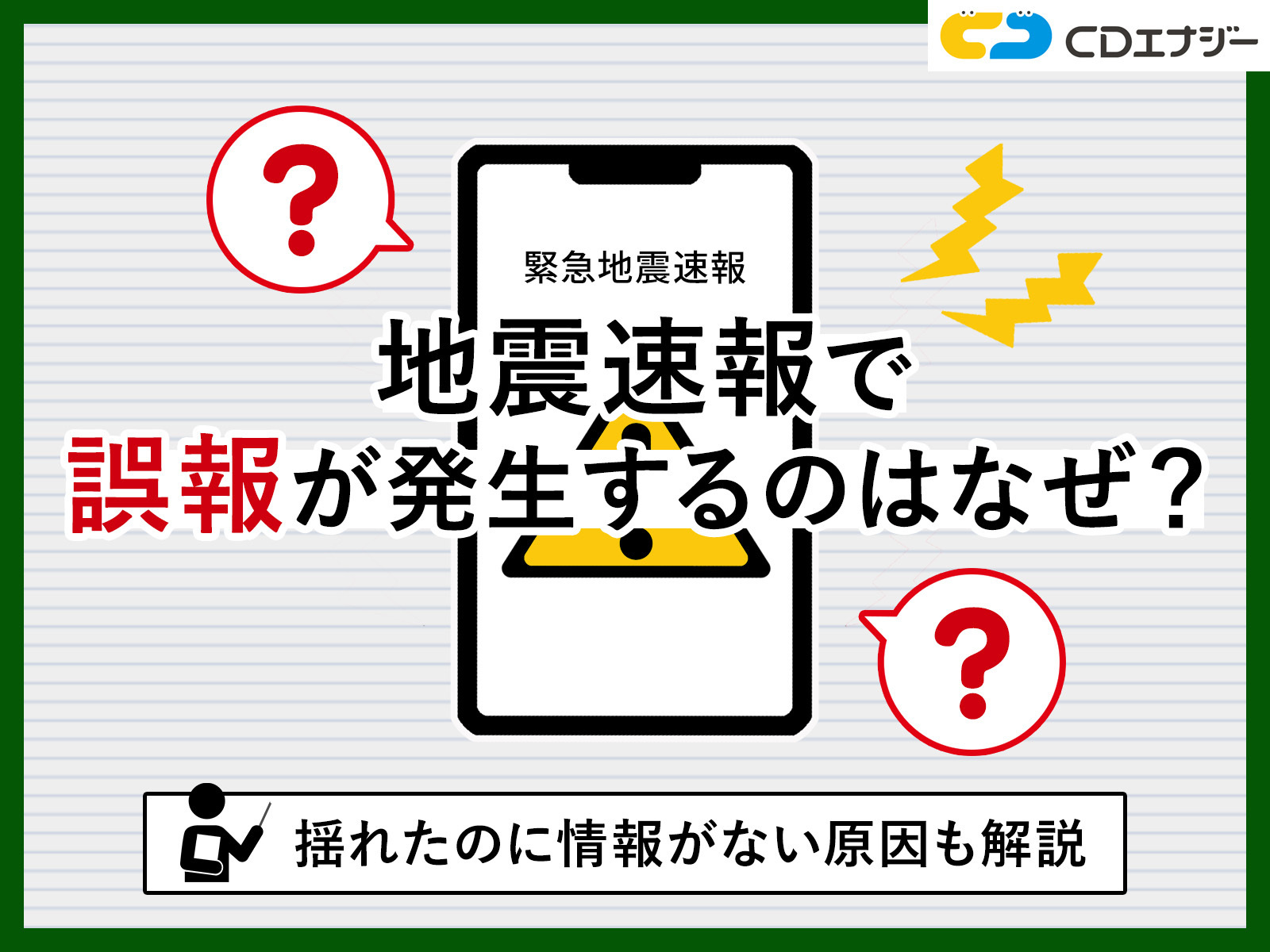
- 地震速報で誤報が発生する原因
- 1. 観測データが少ないため誤差が出る
- 2. 地震観測網が遠いため誤差が出る
- 3. 複数の地震を1つと誤認して誤差が出る
- 4. 地震以外の揺れを検知して誤報が出る
- 5. 地震システムが誤作動を起こすことがある
- 揺れたのに地震情報・速報がない原因
- 1. 震度1以上の観測がない
- 2. 震源の近くでは速報が間に合わない
- 3. 予測震度が急に上がって速報が間に合わない
- 4. スマホの緊急速報の受信設定がOFFになっている
- 地震が発生した際に取るべき行動
- 1. 身の安全を確保する
- 2. 地震の揺れがおさまったら避難する
- 3. 情報収集や状況確認をおこなう
- 緊急地震速報に関するよくある質問
- 緊急地震速報の仕組みは?
- 緊急地震速報はいつから始まった?
- 緊急地震速報が開始されたきっかけは?
- 地震速報は誤報だと思わず身の安全を確保しよう
地震速報で誤報が発生する原因

地震速報で誤報が発生する原因は、主に5つあります。
地震速報は迅速性が求められる一方で、上記のような要因で誤報が発生することがあります。ここでは、それぞれの誤報の原因について解説します。
1. 観測データが少ないため誤差が出る
観測データが少ない場合、限られたデータをもとに震源や規模を推定するため、予測に誤差が生じることがあります。特に観測点が少ない地域では情報が不足し、予想される震度に±1程度の誤差が出ることも珍しくありません。
その結果、緊急地震速報の基準を満たさず、速報が出ないケースもあります。
2. 地震観測網が遠いため誤差が出る
震源が地震観測網から100km以上遠く離れている場合、震源やマグニチュードの推定に誤差が生じやすくなります。
さらに、深い場所で起こる深発地震では、震源から離れた場所で強く揺れる異常震域が起きやすいことや、従来の方法では正確な震度の推定が難しいことなどから、誤差が出やすくなります。
3. 複数の地震を1つと誤認して誤差が出る
短時間かつ近接した場所で複数の地震が発生すると、システムがそれらを1つの大きな地震と誤って認識することがあります。この誤認により、震源やマグニチュードの推定に誤差が生じ、速報の精度が低下します。
4. 地震以外の揺れを検知して誤報が出る
観測点が少ない段階では、事故や落雷、大型車両の通過などの揺れを地震と誤認し、誤った緊急地震速報が出されることがあります。実際に、2016年8月には落雷が原因で緊急地震速報が発表されましたが、これは1地点のみの観測データを元に発表されたものでした。
通常は複数の観測点で確認した時点で発表する仕組みになっていますが、状況によっては誤った情報が出ることがあります。
5. 地震システムが誤作動を起こすことがある
地震の観測や解析をおこなうソフトフェアの不具合によってシステムが誤作動し、実際には地震が発生していないのに速報が出されることがあります。
2011年の東日本大震災のあと、活発な地震活動の影響で誤報が相次ぎました。気象庁はソフトウェアの改修をおこない、誤報を減らすことに努めていますが、完全にはなくなっていません。
揺れたのに地震情報・速報がない原因

地震の揺れを感じたのに、地震情報や速報が届かない場合、以下のような原因が考えられます。
多くは地震の性質によるものですが、場合によってはスマホの設定が原因です。ここでは、速報が届かない原因について解説します。
1. 震度1以上の観測がない
揺れが震度1未満の場合、地震情報が発表されないことがあります。震源が浅く小規模な地震では、揺れを感じる範囲が非常に狭くなるためです。
このようなケースでは、地震の揺れを体感した人がいても公式の情報は出ません。
2. 震源の近くでは速報が間に合わない
内陸の浅い場所で地震が起きた場合などに震源から非常に近い場所にいると、速報が発表される前に強い揺れが到達することがあります。
緊急地震速報は、速度が速いP波をもとに、遅れて来るS波の強い揺れを推定しますが、地震波の解析や伝達には数秒程度かかります。そのため、震源から近い場所では速報が揺れの到達に間に合わないのです。
3. 予測震度が急に上がって速報が間に合わない
地震発生からしばらくして予測震度が上がった場合、速報が間に合わないことがあります。
緊急地震速報は基準となる予測震度を超えなければ発表されません。しかし、地震発生直後は発表基準を下回っていても、その後に大きな揺れが観測されて速報が発表されることがあります。このようなケースでは、地震発生から数十秒経っている場合もあり、速報が出たとしても揺れの到達に間に合わないのです。
4. スマホの緊急速報の受信設定がOFFになっている
スマホや携帯電話の緊急速報の受信設定がOFFになっていると、緊急速報を受け取れません。
大手通信キャリアが販売するほとんどの機種は緊急速報に対応していますが、受信が有効になっているか設定をチェックしましょう。
地震が発生した際に取るべき行動

地震が発生した際には、以下3つの行動を取りましょう。
正しい知識を身につけることで、被害を縮小できる可能性を高められます。ここからは、それぞれの行動について解説します。
1. 身の安全を確保する
地震が起きたら、まずは慌てず落ち着いて身の安全を確保することが最優先です。丈夫なテーブルの下や倒れてくるものがない安全な場所に移動し、頭を守りましょう。
揺れが激しい場合は家具の転倒やガラスの飛散にも注意が必要です。普段から安全な避難場所を確認し、万が一に備えておくことが大切です。
2. 地震の揺れがおさまったら避難する
揺れがおさまったら周囲の安全を確認し、速やかに避難を始めましょう。自宅にいる場合は火の元を確実に消してから避難します。商業施設などでは従業員の指示や館内アナウンスに従い、冷静に行動することが重要です。
屋外にいる場合は、倒壊の恐れがある建物や電柱から離れて、安全な建物内や広い場所へ移動しましょう。海辺にいる場合は津波の危険があるため、ためらわずに高台へ避難してください。
3. 情報収集や状況確認をおこなう
災害発生後は、正確な情報を集めて状況を把握することが大切です。テレビやラジオ、防災行政無線、自治体や気象庁の公式発表を確認しましょう。
SNSも情報収集に便利ですが、誤情報も多いため注意が必要です。周囲の人や避難所と情報を共有することで、安全な行動判断につながります。
緊急地震速報に関するよくある質問
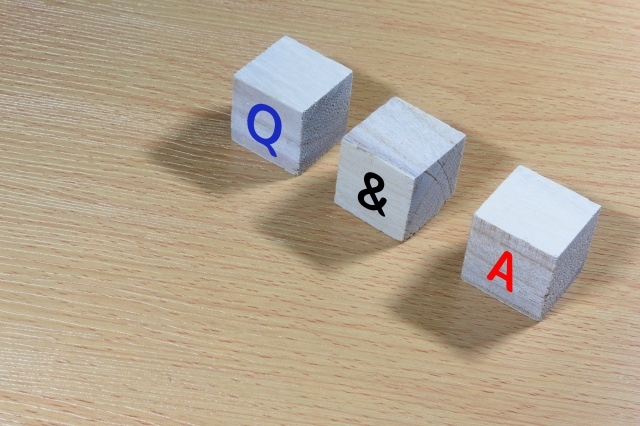
緊急地震速報に関するよくある質問は、以下の通りです。
地震への備えのために、基本的な知識をしっかり押さえておきましょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。
緊急地震速報の仕組みは?
緊急地震速報は、地震発生時に最初に到達する小さな揺れ「P波」を検知し、その情報をもとに大きな揺れ「S波」が来る前に警報を出す仕組みです。
震源付近の地震計がP波を検知すると、自動で震源の位置や規模、予測震度を計算し、S波の到達前に周辺地域に強い揺れが来ることを知らせます。この速報は、個人の安全確保はもちろん、交通機関や工場などでも被害を小さくするために活用されています。
緊急地震速報はいつから始まった?
緊急地震速報は、2007年10月1日から気象庁によって正式に運用が開始されました。大きな被害が予想される地震に対して迅速に警報を発し、住民の安全確保に役立てられています。
緊急地震速報が開始されたきっかけは?
緊急地震速報は、地震による被害を軽減するための取り組みとして始まりました。アイディア自体は古くからあったものの、実現したのはコンピューターの小型化や通信の高速化が進んだためです。また、阪神・淡路大震災後に高感度の地震観測網が整備されたことも、緊急地震速報が実用化された要因の1つです。
地震速報は誤報だと思わず身の安全を確保しよう
緊急地震速報で誤報があったり、揺れたのに地震情報がなかったりすると、誤報だと決めつけたくなることがあるかもしれません。しかし、命を守るためにも緊急地震速報が発表されたら素早く行動しましょう。
地震発生時に身を守るには、まずは頭や体を守り、安全な場所に移動することが基本です。揺れがおさまったら火の元を確認し、避難を始めます。地震発生時は誤情報も出回るため、正しい情報収集を心がけましょう。
緊急地震速報の仕組みや限界を理解し、普段から防災意識を高めておくことが、いざというときの被害軽減につながります。この記事で紹介した内容から、地震速報に関する理解を深めましょう。